 人生・暮らしの考察
人生・暮らしの考察 なぜか流行に乗ってしまうのは人の習性だった
なぜ流行や限定品に惹かれてしまうのか? その理由は「同調の心理」と「希少性の原理」にある。気づけば欲しくなっているのは、人間に共通する自然な習性なのだ。
 人生・暮らしの考察
人生・暮らしの考察 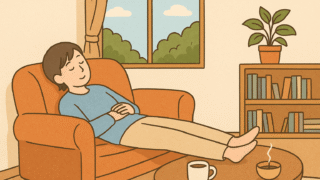 自己啓発・コラム
自己啓発・コラム 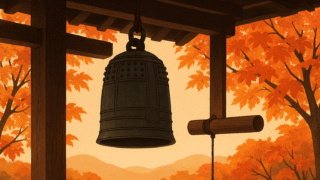 人生・暮らしの考察
人生・暮らしの考察  人生・暮らしの考察
人生・暮らしの考察 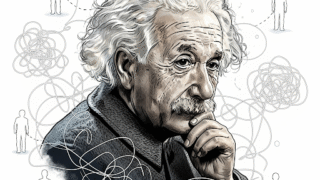 人生・暮らしの考察
人生・暮らしの考察  人生・暮らしの考察
人生・暮らしの考察  人生・暮らしの考察
人生・暮らしの考察 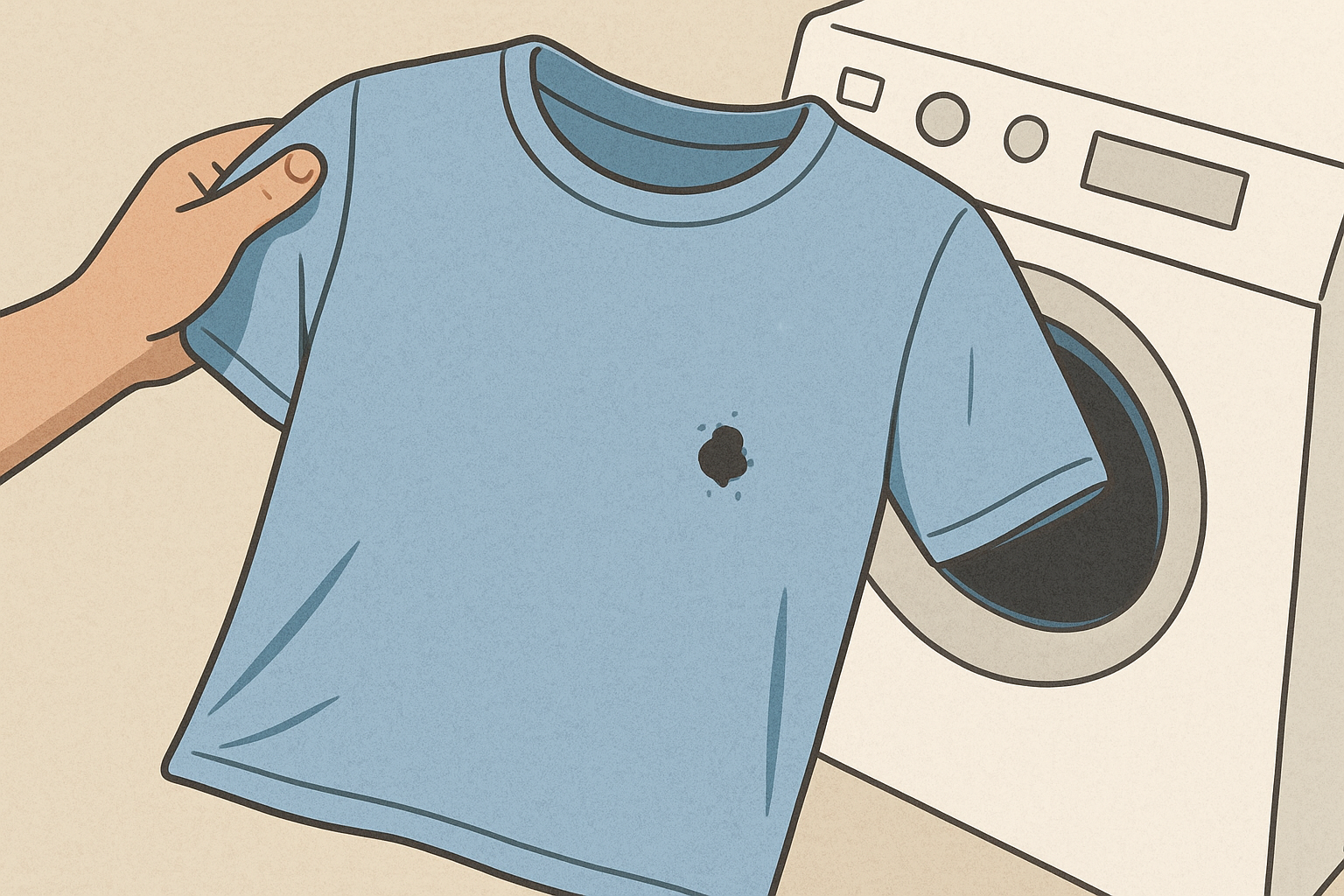 自己啓発・コラム
自己啓発・コラム 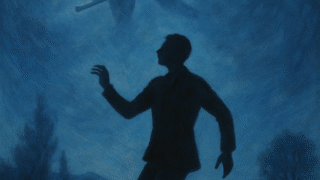 人生・暮らしの考察
人生・暮らしの考察  人生・暮らしの考察
人生・暮らしの考察