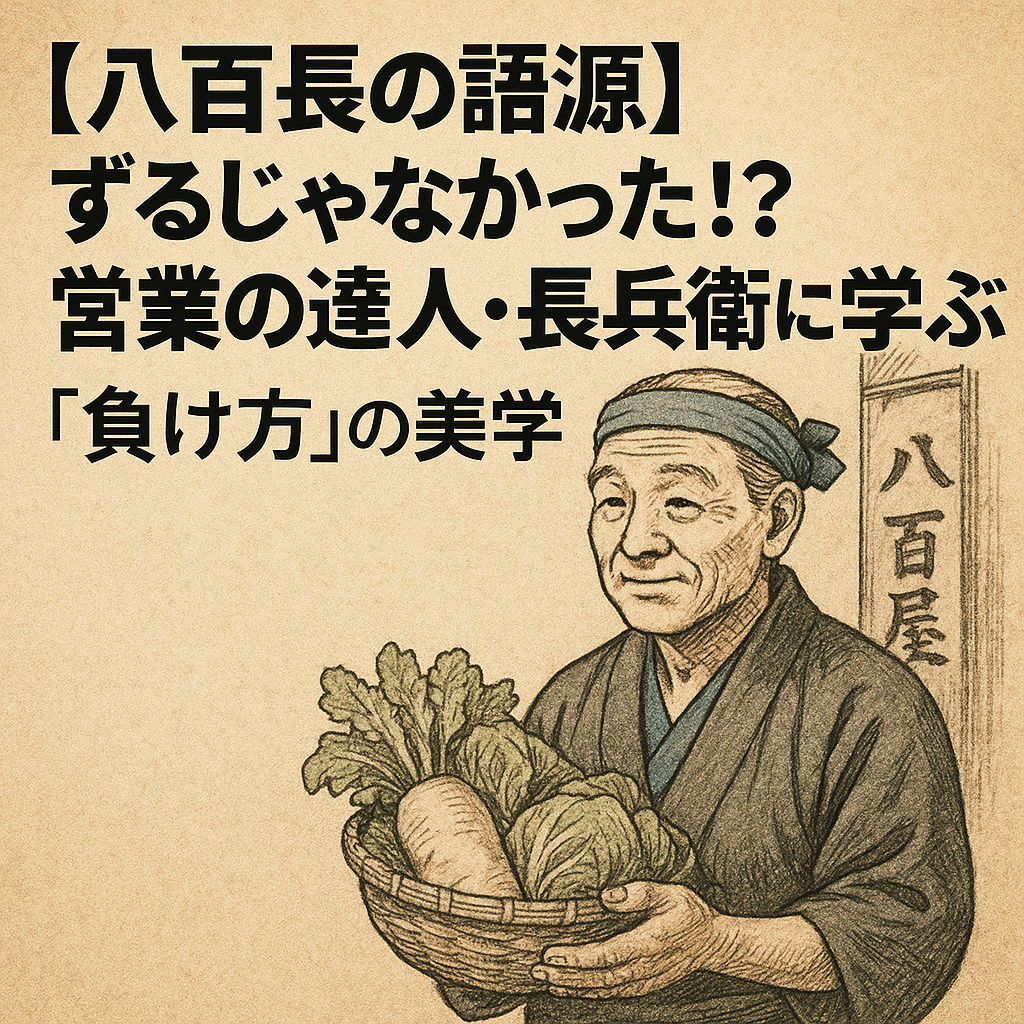世の中には「誤解された言葉」がある。たとえば「八百長」
相撲やプロレスの世界で、あらかじめ勝敗を決める「不正行為」の代名詞として知られているこの言葉。
でも、もともとはもっと人間らしく、もっとあたたかな意味があったことをご存じだろうか。
明治の東京、本所に一人の八百屋がいた。
彼の名は、長兵衛(ちょうべえ)。
腕の立つ八百屋でありながら、囲碁もめっぽう強かったという。
ある日、近所の相撲部屋の親方と囲碁を打つことになる。
長兵衛が本気でやれば、親方など軽く打ち負かせる相手だった。
でも、彼は勝たなかった。
なぜか?
親方にいい気分でいてもらいたかったからだ。
「この人がご機嫌なら、野菜もまた買ってくれるだろう」
そう思ったのかもしれない。
長兵衛の“忖度”がもたらしたもの
やがて親方は喜び、周囲に言いふらす。
「いやあ、俺、あの長兵衛に囲碁で勝っちまったんだよ!」
周りの人たちは苦笑しつつも、その舞台裏を知っていた。
「そりゃ、八百屋の長兵衛が気を利かせて負けてくれたんだよ」
そうして、「八百屋の長兵衛みたいに、わざと負けてあげること」が「八百長」と呼ばれるようになった。
この逸話は、語源由来辞典やWikipediaにも記されており、囲碁での手加減が語源として広く知られている。
八百長は、本当はずるじゃなかった
長兵衛の行動を、あなたはどう思うだろうか?
私はこれを、ひとつの営業術だと思っている。
相手のプライドを守り、機嫌を損ねず、それでいて自分の商売もうまくまわす。
これは立派な「処世の知恵」だ。
今の時代こそ、必要な「負け方」かもしれない
正直なだけじゃ、うまくいかないことがある。
真正面からぶつかれば壊れてしまう関係もある。
ときには、負けたふりをすること。
ときには、引いて相手を立てること。
それが結果的に、長く信頼される道だったりする。
最後に
「八百長」それは本来、ずるではなくやさしさのかたちだった。
そしてそれは今も、営業の現場や人間関係のあちこちで生きている。
あなたがもし「八百長だ」と誰かを笑うときが来たら、ちょっと思い出してほしい。
その裏に、誰かの思いやりが隠れているかもしれないことを。