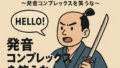気づけば、何もしたくない日が続いていた。
朝がだるい。やることは山ほどあるのに、手が動かない。
自分の中で、何かが止まってしまったような感覚があった。
「怠けているのだろうか」とも思った。
でも、そう決めつけるのは少し早い気もした。
心もまた、慣性の法則で動いている
ふと頭に浮かんだのは、学生時代に習った物理の法則である。
止まっているものは、止まり続ける。
外から何かの力が加わらないかぎり、動き出さない。
これは、物理の基本中の基本、「慣性の法則」である。
人の心も、案外これと似たようなところがあるのではないかと思う。
立ち止まっているとき、すぐに動けなくても、それは仕方のないことなのだ。
力が足りていないだけで、気持ちの問題ではない。
だから、自分を責める必要はない。むしろ「今の私は、止まっているんだな」と気づくだけで十分である。
そこにほんの少しでも外からの力…誰かの言葉や、何かを見て心が動く瞬間が加われば、人はまたゆっくりと動き出せる。
無理に押すと、心が反発してしまう
また、物理には「作用・反作用の法則」というものもある。
押せば、押し返される。力を加えれば、同じだけの力で反発が返ってくる。
「頑張らなきゃ」と強く自分に言い聞かせると、
「でも、もう無理だよ」と心のどこかで反発してくることがある。
それは心が弱いのではなく、自然な反応なのだと思う。
あまり強く押しすぎると、自分の中で逆方向の力が生まれてしまう。
だから、押すならそっとでいい。背中に手を添えるくらいの気持ちで、静かに力を加えるのがちょうどいい。
想像することが、動き出すきっかけになる
アインシュタインは言った。
「想像力は、知識よりも大切だ」と。
目の前の現実がすべてだと思ってしまうと、どんどん苦しくなる。
でも、まだ見えていないものがあると想像できれば、人の心は少し軽くなる。
「自分はこれから変わるかもしれない」その想像こそが、動き出すための最初の一歩になるのだろう。
物理は、何も心を遠ざける学問ではない。
ただ、世界をそういう仕組みで捉えてみる手段のひとつである。
そしてその仕組みは、案外、私たち自身の中にも通じている。
だから、動けない日があってもいい。
その日は、ただの「静止状態」なのだ。
いつかまた、何かの力が加わるときまで、ゆっくり止まっていればよい。