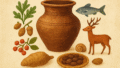住宅街や学校の近くにクマが現れる――そんなニュースを目にする機会が増えた。
「危険な動物が出たなら、警察や自衛隊が対応してくれるのでは?」
そう思う方も多いかもしれない。
しかし実際に現場でクマを駆除しているのは、地元の猟友会という民間のハンターたちだ。
なぜ、銃を持つ公的機関が動けないのだろうか?
今回は、制度と暮らしの“見えない境界線”をわかりやすく解説しよう。
警察は「人命の危機」にしか発砲できない
警察官は拳銃を所持しているが、その使用には厳しい制限がある。
基本的に、発砲が許されるのは「人間の命に直接かかわる緊急事態」のみ。
たとえば、クマが人に襲いかかっている場面であれば発砲の可能性もあるが、単に住宅街に現れただけでは、発砲の条件を満たさない。
さらに、万が一流れ弾が人に当たれば重大な事故につながるため、
警察がクマを撃つことは制度上、非常にハードルが高いのだ。
そのため、警察は現場での避難誘導や交通規制などを担当し、実際の駆除は別の機関に委ねられている。
自衛隊は「防衛」や「災害」以外では動けない
自衛隊もまた、銃を所持する組織だが、出動には明確な法的根拠が必要なのだ。
「防衛出動」や「災害派遣」など、国の安全保障や大規模災害に該当しない限り、クマの出没程度では出動できない。
2025年には秋田県が自衛隊に支援を要請した例もあるが、これは箱わなの設置や駆除後の処理など、あくまで後方支援にとどまる。
つまり、自衛隊が銃を持ってクマを撃つことは、法律上できないのだ。
実際に駆除を担うのは「猟友会」
クマの駆除を実際に行っているのは、猟友会と呼ばれる民間のハンターたち。
彼らは狩猟免許を持ち、自治体から正式に依頼を受けて活動している。
つまり、クマの駆除は「行政からの委託業務」であり、制度的には民間の力に頼っているのが現状だ。
しかしその実態は厳しく、報酬は少なく、危険と隣り合わせ。
山に入って銃を構えるのは、60代〜70代のベテランが中心で、若手の担い手不足も深刻な課題となっている。
なぜクマが町に現れるのか
近年、クマの出没が増えている背景には、環境の変化がある。
山の木の実が減り、耕作放棄地が増え、人と自然の境界が曖昧になってきたのだ。
「クマが人里に下りてきた」というより、
「人がクマの生活圏に近づいている」とも言えるかもしれない。
制度を知ることが安心につながる
クマの駆除は、誰かが担わなければならない現実だ。
しかし、警察や自衛隊が動けないのは、制度上の制限があるからこそ。
その結果、地域の猟友会が“最後の砦”として活動している。
こうした制度の仕組みを知っておくことで、ニュースの見え方が少し変わるかもしれない。
そして、万が一のときに「誰が動けるのか」を理解しておくことは、
私たちの暮らしにとっても大切な備えになるのではないだろうか。