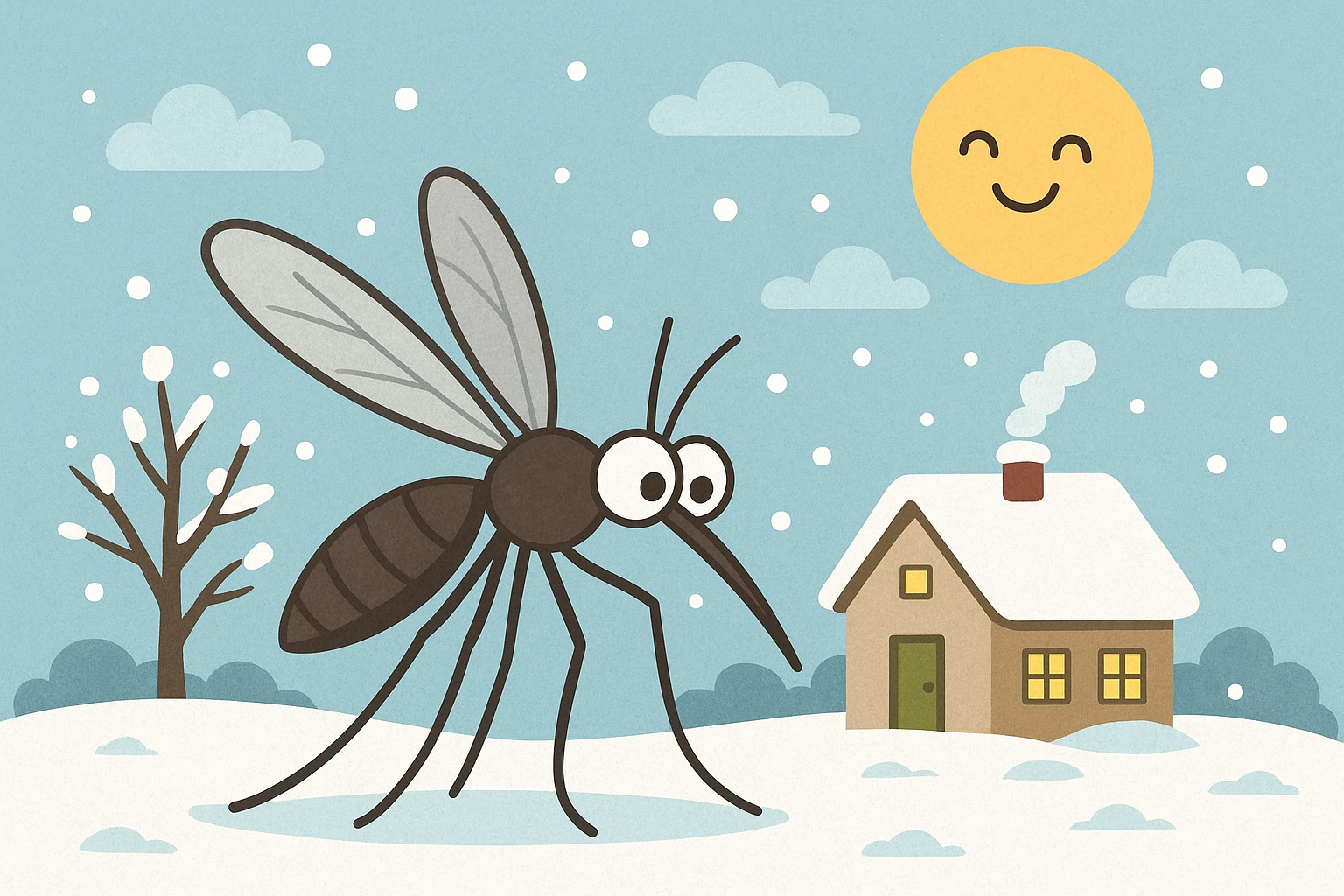「中秋の名月」といえば、ススキである。
黄金色のすすきが風に揺れる様子は、秋の訪れを告げるようでなんとも風情がある。
月見団子とともに供えれば、それはもう完璧な“ザ・日本の秋”といった情景だ。
だが──
このススキ、実は“本来の主役”ではなかったという話をご存じだろうか。
本来、月に捧げるべきは「稲穂」だった
月見は、もともと収穫への感謝と豊作祈願をこめた行事である。
したがって、供え物の主役は自分たちの命を支える「食べ物」。
そのなかでも最も重要なのは、もちろん稲=お米だった。
だから、本来なら稲穂を刈って供えるのがスジだったわけである。
しかし──
問題がひとつあった。
中秋の名月は、旧暦で8月15日。
現代の暦でいえば9月中〜下旬あたりになるが、この時期、稲はまだ刈り取り前のところも多かった。
要するに、稲穂が手元にない。あるいは、まだ刈りたくない。
そこで人々は考えた。
「それっぽく見えるもので、代用できないか」と。
そして現れた、ススキという影武者
そんなとき目に留まったのが、野に揺れるススキである。
黄金色で、細長くて、穂が出ていて、なんだか稲に似ている。
よし、これでいこう。
こうして、稲の“ふりをした”ススキが、月見の供え物として採用された。
以後、時代が進むにつれて「ススキ=月見の象徴」として定着していったのである。
いまや本来の稲穂を飾る家庭などほとんどなく、
ススキの方がすっかり“正統派”の顔をしている。
なんとも日本らしい、“なんちゃって文化”の完成である。
魔除けの意味? それも後づけかもしれない
ススキには「霊を寄せ付けない」「病気除けになる」といった魔除けの効果があるとされている。
そのため、月見が終わったあとにススキを玄関や軒先に吊るす家もある。
けれど、この説もどうやら後づけの意味付けらしい。
「代用品だけど、ちゃんと意味があるよ!」
と言ってあげたくなる、やさしい嘘のようでもある。
“本物”より“影武者”が主役になるという現象
ススキに限った話ではない。
月見団子だって、かつては里芋を供える「芋名月」の方が本流だった。
だが今では、芋より団子の方が“本番”のように扱われている。
影武者が本物を超える瞬間。
それはどこか可笑しくて、少し切ない。
だが、人が求めているのは“真実”よりも“それっぽさ”なのかもしれない。
まとめ:ススキは“代用品”だった。でも、それでいい。
ススキは稲の代わりだった。
最初は“間に合わせ”として飾られていただけだった。
けれど、いまやその姿は、月夜に最も似合う“名脇役”として、多くの人の記憶に残っている。
本物でなくても、代用品でも、人の心を動かすことはできるのだ。
ススキのように、誰かの代わりでも、風に揺れて美しければ、それでいい。