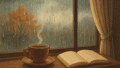赤く塗られた休みの不思議
もうすぐ敬老の日である。
カレンダーには赤く印がつき、休みが一つ増える。
日本は祝日の多い国で、年間16日ほどあるとされ、世界的に見てもトップクラスだ。
しかし、祝日が多いからといって、日本人が自由に休めているかというと、どうも怪しい。
有給が使えぬ国民性
日本人は有給を取らない。
いや、正確には「取りたくても取りづらい」。
上司の顔をうかがい、同僚に気を遣い、結局は机に張りつく。
厚生労働省のデータによれば、有給消化率はおよそ50%程度。
つまり半分は消えないまま年を越すのだ。
そこで国が登場し、「この日は休め」と命じる。
ありがたいことではあるが、同時に奇妙である。
赤い日がなければ休めない国民性とは、一体どのような自由なのか。
欧米との対照
欧米では状況が逆だ。
アメリカは祝日が十日ほどしかない。
ヨーロッパも同様で、国によっては年間祝日が10日未満の国もある。
しかし、彼らは自らの判断で休暇を取り、数週間の長期休暇に出かける。
カレンダーがどうであろうと、自由に休むのである。
赤い日が少ないからといって、働き詰めになるわけではない。
自由の皮肉
一方、日本は赤い日でなければ休めない人が多い。
自由を与えられたはずなのに、自由を使えない矛盾である。
こうして一年のうち、祝日がこれでもかと差し込まれる。
国が休みを与えてくれるから休めるのか、国に頼らなければ休めないのか、考えれば考えるほど皮肉な仕組みである。
敬老の日の本当の意味
敬老の日は老人を敬う日である。
しかし、実際には働き詰めの人間に休みを与えるための日でもある。
もっとも、自ら休む勇気を持たない限り、赤い日を増やすしかないのだが。
カレンダーの赤に頼らぬ自由は、まだ遠いのかもしれない。
リンク