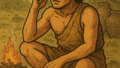秋の虫の声は雑音か、それとも音楽か
秋の夜、窓の外からコオロギや鈴虫の声が聞こえてくる。
「リーンリーン」「チンチロリン」と繊細に響く音色は、季節の印のようである。
私の耳には風流に聞こえるこの音も、外国人にとってはただの雑音でしかないらしい。
日本人と欧米人で違う脳の反応
京都大学の研究によれば、日本人が虫の声を聞くと脳の左脳、言語や音の高低を処理する部分が活性化する。
一方、フランス人など欧米人では右脳、環境音を処理する部分が活発になるという。
日本語は高低差で意味が変わるため、脳は虫の声も「ことばや旋律のように」認識してしまうのだ。
コオロギや鈴虫の他にもマツムシやクツワムシなど、秋の虫は多種多様で、それぞれ鳴き方や音色が異なる。
窓を開け、虫の声に耳を澄ませば、脳が無意識に処理する音の多層性に気づき、秋の夜の深みを感じられる。
同じ音でも、日本人には音楽、欧米人には雑音。
自然の音をそのまま楽しむ習慣は、日本ならではの感覚かもしれない。
耳に届く音は同じでも、脳の解釈が違えば世界は変わる。
虫の声ひとつでも、人それぞれの世界があることを思い知らされるのだ。