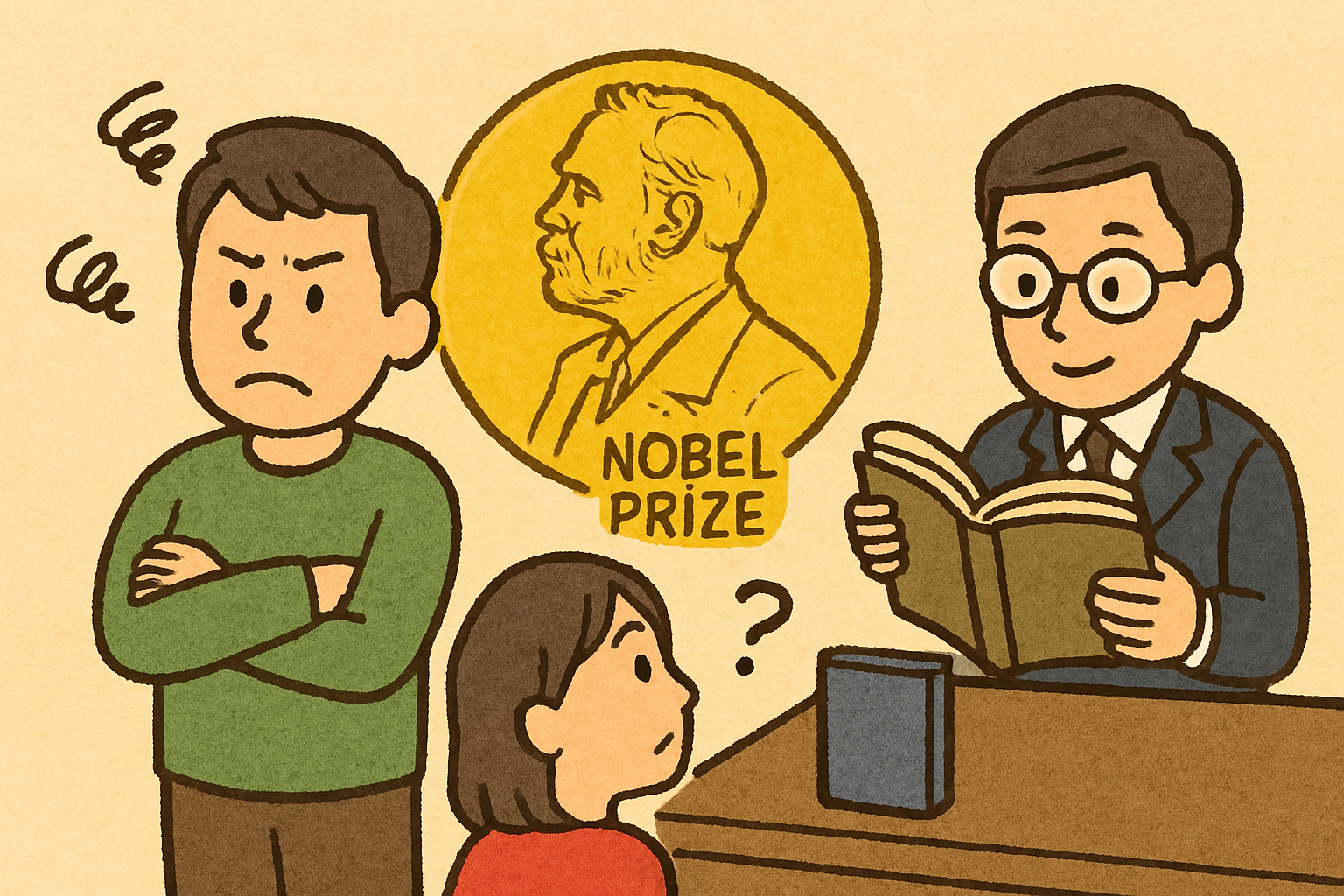ノーベル賞の季節になると…
毎年秋になると「ノーベル文学賞は○○氏に決定!」というニュースが流れる。
でも正直、私はこう思う。
「誰?読んだことないけど?」
「ていうか、翻訳で読んで文学賞ってどうなの?」
文学って“言葉の芸術”じゃなかったっけ?
その“言葉”を別の言語に置き換えて評価するって、なんか納得いかない。
そもそも、誰が選んでるの?
選んでいるのは、スウェーデン・アカデミーという18人の文学者や学者たち。
彼らが1年かけて、世界中の作家の中から「今年の文学王者」を決める。
でも、選考の中身は50年間非公開。
誰が推薦したかも、どんな議論があったかも、私たちにはわからない。
「え、そんな秘密主義で決めてるの?」
「庶民の感覚、入ってないじゃんw」
選考の流れはこんな感じ(ざっくり)
1. 推薦受付(9月〜1月)
→ 世界中の大学教授や文学者が「この人いいよ!」と推薦
2. 一次選考(2月〜3月)
→ 数百人の候補から20〜30人に絞る
3. 二次選考(春〜夏)
→ さらに5人程度に絞って、作品を精読
4. 最終選考(10月)
→ 18人の委員が投票。過半数で決定!
でも、原文を読める委員は限られている。
だから、翻訳された作品を読んで評価することがほとんど。
翻訳で文学賞って、もう別の作品じゃない?
たとえば川端康成の『雪国』の冒頭
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」
→ 英訳では “The train came out of the long tunnel into the snow country.”
韻も余韻も消えてるし、詩的な美しさはどこへ?
それを読んで「この作家は素晴らしい!」って言われても…それ、翻訳者の手柄じゃない?
実際、川端康成は「翻訳者にも半分の名誉を」と語っていたそう。
結局、文学賞って“審査員の評価”であって“読者の共感”じゃない
だからこそ、庶民が思う「納得いかないw」は、文学の本質を突いている。
文学って、読む人の人生と響き合ってこそ。
ノーベル賞よりも「自分の心に残った一行」のほうが、ずっと価値があるのかもしれない。