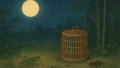猛暑とビールの思い
温暖化のせいか、今年もまた猛暑日が続く。
おかげで私のビールの消費もうなぎ登りだ。
こんな暑さの中、ビールを発明した人にノーベル賞をあげたいくらいだと思った。
ふと考えると、ビールの起源は一体いつなのだろうか。
調べてみると、メソポタミア文明の時代には、麦を煮て作った粥をうっかり放置していたら、空気中の酵母が入り込み自然に発酵してしまったことが始まりであった。
当時のビールは、今のようにホップで苦みをつけたものではなく、甘く濁っていて、どろっとした液体のパンのようなものであった。
栄養も摂れる、保存食でもある。
ただの「うっかり」が、今日の乾杯の味につながっていると思うと、少し笑えてくる。
ローマ時代のワイン
ローマ時代にはワイン文化が中心であった。
ブドウを摘んで置きっぱなしにして自然に発酵させたものが飲まれていた。
ローマ時代は地域によって飲み物の嗜好が異なった。北方の諸民族は主にビールを愛飲していたらしい。
どちらも偶然の産物である。
人間の不注意が、文明に思いもよらぬ贈り物をしてくれたのだ。
人間の自堕落が生んだ食文化
ならば、他にも人間のうっかりや適当さが生んだ産物はあるだろうか。
調べてみると、面白いくらいに枚挙にいとまがなかった。
- チーズ:羊や牛の乳を革袋や甕に入れたまま忘れていたら、自然に固まって酸味がついた。最初に口にした人は「腐ってる…?」と思ったに違いない。
- ヨーグルト:牛乳を暖かい場所に置きっぱなしにしたら乳酸菌が繁殖し、酸っぱく固まった。失敗作かと思いきや、偶然の保存食兼健康食品である。
- パン:小麦粉と水を練った生地を放置したら自然に発酵して膨らんだ。膨らみすぎて腐っているかもと思いつつ焼いたら意外にうまかった。
- コーヒー:山羊が赤いコーヒーの実を食べて元気に跳ね回るのを見て、人間も試してみたのが始まりである。偶然の行動が新しい飲み物を生んだ。
- 味噌・しょうゆ:大豆や麦を塩とともに甕に入れ、数か月放置したら、カビや酵母が働き、旨味たっぷりの発酵食品に変わった。
- 納豆:煮た大豆を藁に包んで数日放置したら糸を引く不思議な豆になった。普通なら捨てるところを「これはこれで…」と食べた先人の勇気である。
- ペニシリン:実験用シャーレを片付け忘れたらカビが生え、偶然そのカビが細菌を殺していた。医学史上最大のうっかり発見である。
偶然と勇気が文明を作る
これらに共通しているのは、放置や忘れ物が偶然の発酵や発見につながったことである。
さらに、もう一つ共通しているのは、最初に口にしたり使ってみたりした人間の勇気である。
少し怖くて、少し適当で、少しもったいない。
その心が、我々の食文化や科学の発展を支えてきたのだ。
ビールもチーズも納豆も、すべて人間の自堕落と少しの好奇心から生まれた贈り物である。
最後に思うのは、現代の私たちは冷蔵庫や調理器具のおかげで、偶然の産物を自ら作らなくても楽しめるということだ。
しかし、昔の人々のように「放置してみる勇気」と「もったいない精神」を持っていたら、今よりももっと奇想天外な味の世界が広がっていたかもしれない。
人間のうっかりは、文明の宝箱を開ける鍵でもあったのである。