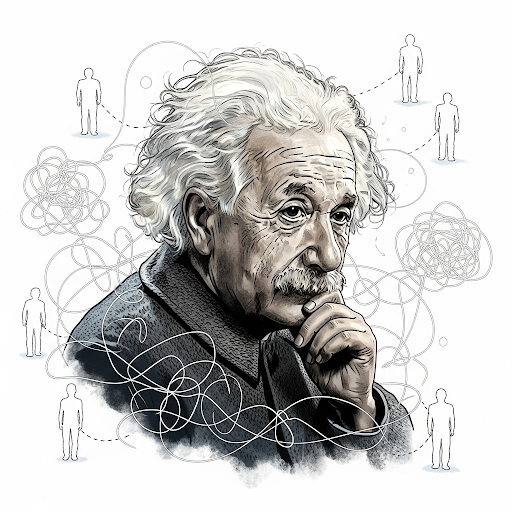アインシュタインも、ただの“おじさん”だった
天才の素顔は、私たちと変わらない
「私は自然については少し理解をしていますが、人間については全く理解していません。」
──アルベルト・アインシュタイン
この言葉を読んだとき、私はちょっとだけ笑ってしまった。
あの相対性理論を生み出したアインシュタインが、人間については「まったく理解できない」と言っている。
そうか、天才でも人間関係には悩むのか──と、なぜかホッとしたのだった。
アインシュタイン家の嫁姑問題
「わたしの母は、だいたいにおいていい性格の持ち主ですが、姑としては、まったくの悪魔です。彼女がわれわれ夫婦と一緒にいるとき、まわりはダイナマイトでいっぱいになってしまいます。」
──アルベルト・アインシュタイン
ダイナマイトとは、なかなかの表現である。
爆発寸前の空気が日常的にあったのだろう。
アインシュタインが仕事から戻るとき、玄関のドアノブにそっと手をかけながら、「今日こそ何も起きませんように」と願っていたのかもしれない。
世間一般の家庭における「嫁姑問題」は、どうやら天才の家でも例外ではなかったらしい。
妻との相性も「相対的」だった?
「今の妻は科学を理解出来ないのは嬉しいことです。最初の妻はできたのです。」
──アルベルト・アインシュタイン
科学を理解する女性が合うとは限らない。
むしろ、あまりに分かりすぎるがゆえに、衝突もあったのかもしれない。
アインシュタインは最初の妻ミレヴァと大学時代からの知り合いで、物理的議論も交わしていたという。
だがその関係が、やがて“ライバル”や“監視者”のような重さになっていった可能性もある
再婚相手のエルザは科学とは無縁の人物だったが、むしろその距離感が彼には心地よかったのだろう。
知的共鳴よりも、感情の安定を求めるようになった。
そんな変化も、人間らしくて興味深い。
キュリー夫妻はうまくいったのに?
キュリー夫妻の話を知っている人はこう思うかもしれない。
「学者同士でも、ピエールとマリは仲がよかったじゃないか」と。
実際、1903年にピエール・キュリーとマリ・キュリーは、夫婦でノーベル物理学賞を受賞している。
二人は放射線研究において完全に協力し合い、まさにパートナーとして歴史に名を刻んだ。
だがそれも、稀有な例だ。
研究と生活、その両方で波長が合う相手など、そうそういるものではない。
アインシュタインは“理屈”の世界に強かったが、“情”の世界では不器用だったのかもしれない。
「人は皆同じ」──その意味は?
「人は皆同じ。」
──アルベルト・アインシュタイン
最初にこれを読んだときは、「そんなこと言っても、あなただけは別でしょ」と思った。
けれど文脈を辿ると、それは彼なりのやさしさだったのではないかと思い直した。
「私も悩んでいる。あなたも悩んでいる。だから私たちは“同じ”なのだ」と。
社会的地位やIQの高さに関係なく、人は皆、心のどこかに不安や葛藤を抱えている。
その事実を彼は認め、受け入れていたのかもしれない。
天才も、人の心ではつまずく
「私の人生は一人の人間として見れば失敗だったが、科学者としては成功だった。」
──アルベルト・アインシュタイン
あのアインシュタインでさえ、自分の人生を「失敗だった」と表現している。
成功とは何か、幸せとは何か──それを考え始めると、天才でも迷子になるのだ。
悩んでいるあなたへ、天才からのメッセージ
アインシュタインというと、黒板の前で難しい数式を並べる姿を思い浮かべる。
だがその裏には、姑に気を遣い、妻との相性に悩み、人間関係の複雑さに戸惑う姿があった。
彼はこう言っている
「常識とは、18歳までに身につけた偏見のコレクションである。」
──アルベルト・アインシュタイン
私たちが「普通」だと思っていることも、誰かにとってはまったく通用しない。
だからこそ、うまくいかない日があっても仕方がない。
アインシュタインだって、つまずいていたのだから。
天才がそれなら、私たちが悩んで当然ではないか。
完璧じゃなくていい。むしろ、不完全こそが人間らしさだ。