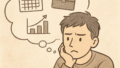ゾッとする話に、癒やされている不思議
夏になると、決まって怪談話が持ち出される。
テレビでは「○○が見た心霊体験」、YouTubeでは「実話怪談」なるものが次々と再生される。
しかも、どれも“納涼企画”として紹介されるから面白い。
あんなにゾッとする話を聞いて、なぜか「涼しい気がする」というのだ。
だが、考えてみればこれは妙な話である。
気温は下がらないのに、なぜ“涼しく感じる”のか
怪談を聞いたからといって、部屋の温度が下がるわけではない。
けれど、聞いているうちに背筋がスッと冷えるような感覚になる。これはなぜか。
心理学的にいえば、「恐怖」と「身体の冷感」は密接な関係にある。
人は恐怖を感じると、交感神経が活性化し、筋肉が収縮する。
このとき、血流が一時的に減少するため、皮膚の温度がわずかに下がるとされている。
つまり、「背筋が寒くなる」感覚は、実際に身体でも起きている現象なのだ。
だが、それでも気温が2度も3度も下がるわけではない。
あくまで“感覚”の話である。
涼しさより「ゾワッとする快感」?
怪談話が好きな人に理由を尋ねると、こんな答えが返ってくることがある。
「怖いけど、なぜかクセになるんです」
「背筋がゾワッとする感じが、逆に落ち着く」
これは、心理学でいう「スリルによる快感」に近い状態で、
恐怖や不安を“安全な環境で”疑似体験することで、脳が興奮し、快感物質(ドーパミン)を分泌するという説もある。
つまり、怪談話の“涼しさ”とは、暑さをしのぐための冷却効果というより、
「安全に背筋を凍らせて遊ぶ」ための娯楽なのかもしれない。
文化としての「納涼怪談」
納涼と怪談の組み合わせは、実は江戸時代からあった。
真夏の夜に行われた「百物語」などは、まさにその典型である。
蝋燭を百本灯し、怪談を一話ごとに消してゆく。
最後の一話を終えたとき、すべてが闇に包まれる。
その“暗さ”と“静けさ”のなかで、人々は恐怖を味わい、
そのあとの日常に、少しの安心と涼しさを見いだしていたのかもしれない。
思い込みでも、感じられる“涼”
怪談は、実際の温度を下げてくれるわけではない。
けれど、「涼しくなった気がする」という思い込みが、
この暑さをやり過ごす、ひとつの知恵だったのだろう。
冷房もなかった時代に、人は“想像”で涼を得ていた。
現代の我々がそれを笑うことなど、できはしない。
むしろ、
「気のせい」によって暑さを乗り切るという、その柔らかさこそが、
夏の怪談文化の奥ゆかしさなのかもしれない。
「もっと涼しくなりたい人は、こんな本でも──」