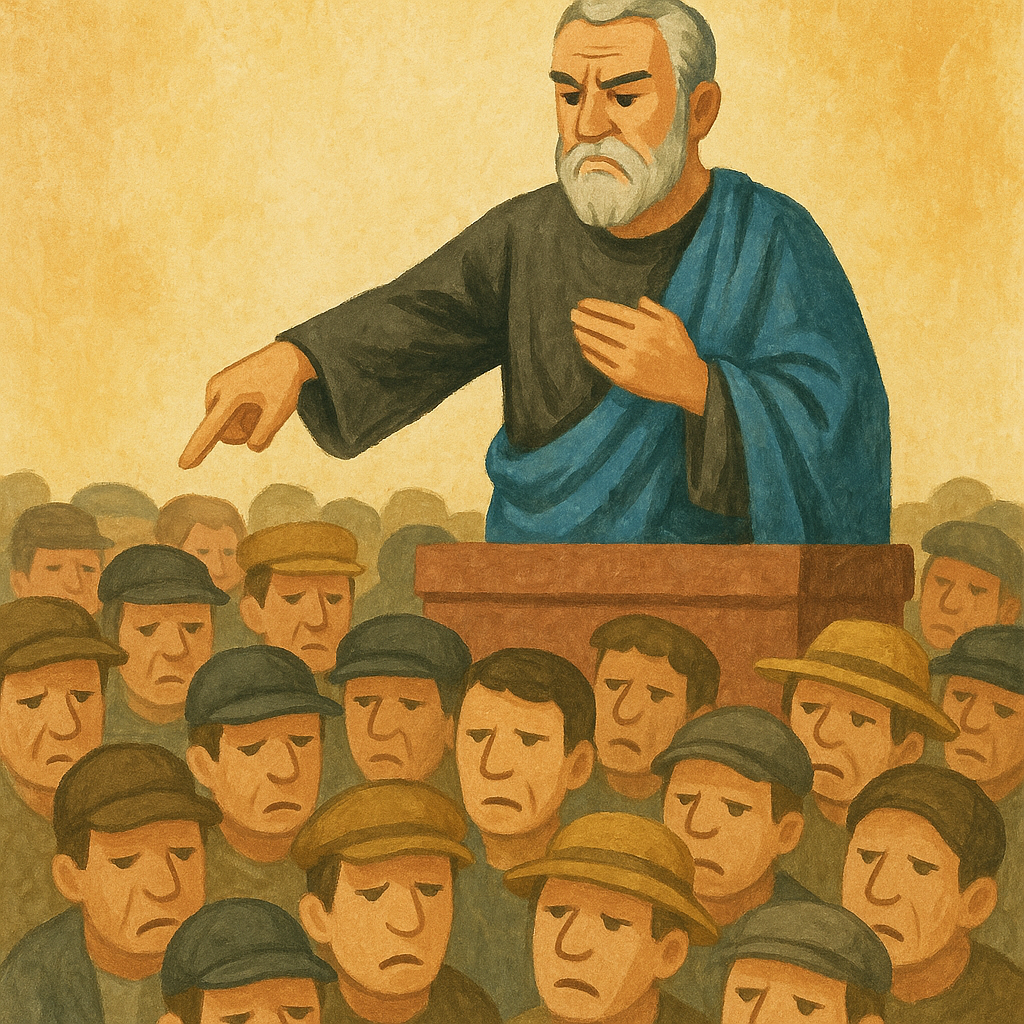「愚民の上に賢人を戴くことは、これなし。
愚民は愚官を生ずるのみにして、未だ賢官を生ずるの例なし」
――福澤諭吉『学問のすゝめ』
この言葉は、社会の現実を鋭く突いている。
たとえ賢いリーダーが現れても、愚かな民衆がそれを支えるのであれば意味がない。
結局は、民衆の知的レベルがそのまま社会の質を決めるのだ。
社会の質は「選ぶ側」が決める
政治や社会の未来は、「誰を選ぶか」ではなく、
「選ぶ側がどれだけ考えているか」にかかっている。
学ばず、考えず、ただ流される民衆の中からは、
健全なリーダーは生まれにくい。
そして、たとえ優れたリーダーが現れても、理解されず、潰されてしまう。
教育の価値を忘れた社会に未来はあるか
しかし、教育の価値はどこにいても変わらないはずなのに、先進国では「当たり前」として扱われ、そのありがたみが薄れているようにも感じられる。
一方、経済的に厳しい地域では、子どもが家計を支えるため学校に通えない現実がある。
学ぶことが「特権」である場所が今も存在し、行政が改善を試みるも、十分に手が届いていないのが現状だ。
発展途上国の現場が教えてくれること
インドの農村で出会った子どもたちは、学ぶことの意味を深く教えてくれた。
整った教室や新しい教材がいつもあるわけではない。
狭いスペースで、時には屋外で、限られた教科書や道具を手にしながらも、真剣な眼差しで知識を求めていた。
彼らにとって「学び」は単なる知識の習得ではない。
未来を切り開くための、生きるための必須の力なのだ。
だからこそ、一人ひとりが学ばなければならない
福澤諭吉は150年前に警告した。
社会を変えるのはリーダーではなく、考える民衆の総和だと。
一人ひとりが学び、考え、行動しなければ、
未来は同じ愚かな繰り返しに終わってしまう。
学びとは、人生を他人に委ねない力である。
学びとは、自分の頭で問い、選び、行動する力である。
学びは知識のためではなく、
社会の質を高めるための基盤であり、
自由を勝ち取るための武器だ。
今こそ福澤諭吉の言葉を胸に刻み、
愚かでない民衆として未来を選び取る力を育てたい。